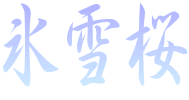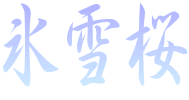はらはらと白い花弁が雪のように降り注いでいる。
天空には朧に霞む臥し待ちの月。
けむるような春の宵に、白い鬼は沈んでいた。
「さくら…か…」
白い鬼は無機質なまでに動こうとしない感情の底で呟く。
「また…貴女なのか…湧泉(わくのいずみ)…」
白い鬼の端正な顔に微かな自嘲が浮かぶ。
降りしきる花弁にその身を任せたまま、白い鬼は静かにその長い睫を閉じた。
白い夜着をきちんと合わせ、少年は座敷の隅に正座していた。
宗方志郎篁(むなかた しろう たかむら)。この少年はようやく十二になる宗方の長子である。
幼い頃から聡明で忍耐強く、長ずれば申し分のない一族の宗主となるだろうと、誰もが期待をかけていた。
宗方の家は、平家の流れを汲む由緒正しい家柄ではあったが、時世の流れは決して一族に味方するものではなかった。
没落の一途をたどる一族を支えるはずの志郎篁の父は、武士とは名ばかりの貴族趣味の貴人で、ほとんど家には寄りつかず放蕩な生活を送っていた。
変わって家を支えていたのが、年の離れた篁の姉、湧泉だったのである。
庭の桜が満開の花をつけている。
絶え間なく降りしきるその花弁を見ながら、篁は冷え冷えとした雪を思っていた。
困窮している宗方の家のために、これまで湧泉のやってきたことを篁は薄々感づいていた。
湧泉は、その類稀な巫女の資質を持って、呪詛呪殺を請け負っていたのである。
彼女はこれまで二度、他家に嫁いだが、そのたび夫が変死を遂げ実家に戻ってきている。
原因を追究することもなく。人々は一様に口を噤(つぐ)んだ。
禍が己の身に降りかからぬように。
瞬きをほとんどしないその蛇のような瞳は、目を合わせた相手を例外なく沈黙させる力を持っていた。
だが篁が何より恐ろしかったのは、姉が呪術を操ることよりも、平然と、むしろ喜びをもって人を殺せる気質の持ち主であると言うことだった。
____だが、湧泉は篁を溺愛していたのである。
花冷えのする座敷に一人、篁は湧泉を待っていた。
姉の命令は絶対であり、逃げることは許されない。
暗澹たる気持ちのまま、篁は姉の訪れを待っていたのである。
焚きしめられた香の薫りが、篁の頭の芯を鈍らせている。
ぬるま湯に浸かっているときのような奇妙な開放感。
だが、感覚は奇妙なほど冴えており、頬を撫でる風の感触にすら敏感になっていた。
桜の木の上に臥し待ちの月が姿を見せている。
夜半を過ぎているのがぼんやりとそれでわかった。
「志郎」
名を呼ばれ篁ははっとして顔を上げた。
いつからそこにいるのか、白い夜着の湧泉が、敷かれた布団の上に座っていた。
「姉上…」
篁は困惑する。
姉の訪いの意味が、幼いながらおぼろげに理解出来たからだ。
「こちらにいらっしゃい、志郎。この宗方の家のためにも貴方には早く大人になっていただかなくてはならないのです…」
湧泉の白い腕が、緩やかに篁を手招きする。
少年はきつく目を閉じると立ち上がった。
桜が降り注いでいる。
篁にとっては桜は常に、姉湧泉の幻を連れてきた
風に舞う花弁がその体に纏いつくように、湧泉の気配は篁を捉えて離さなかったのである。
長じて篁は、縁者の勧めで春日と言う名の妻を娶った。
宗方の家に跡継ぎを残すためである。
幼い頃からの姉との関係で、篁の中には根深い女性不信があった。
女性に対し不器用で臆病な態度が、その類稀な美貌とあいまって女嫌いの冷血漢という仮面を篁に被せていた。
春日は幼いながらもそんな篁を理解しようと努めていた。
またそれ以上に篁自身が、妻を娶ることで姉との関係が絶てることを望んでいたのも事実だった。
湧泉は、体調の不調を理由に婚姻の宴には姿を見せなかった。
初夜の晩、新床で頬を染める妻を抱きながら篁は、自分の中にある湧泉の気配を払拭しようとしていた。
「志郎様…」
絡めた指に力が込められる。
篁の胸に妻に対する愛しさが沸き上がる。
その時。
ふわりと桜の花弁が、新妻の胸元に舞い落ちた。
「…!?」
篁の瞳は、ありえないものを映して大きく見開かれる。
「志郎様…?どうなさいました?」
自分を見上げる妻の顔は、姉湧泉のそれではないか。
「うわあああっ!!」
狂ったように舞い踊る桜。
差し伸べられる白い腕。
篁は、耐え切れず初夜の床を逃げ出した。
闇の中で白い顔が笑う。
降り注ぐ花弁が呼吸の自由さえ奪っていく。
甘やかな薫りの毒に白い鬼は身じろぎした。